本稿では、人権方針を策定するための7つの実践ステップのステップ4を解説しています。
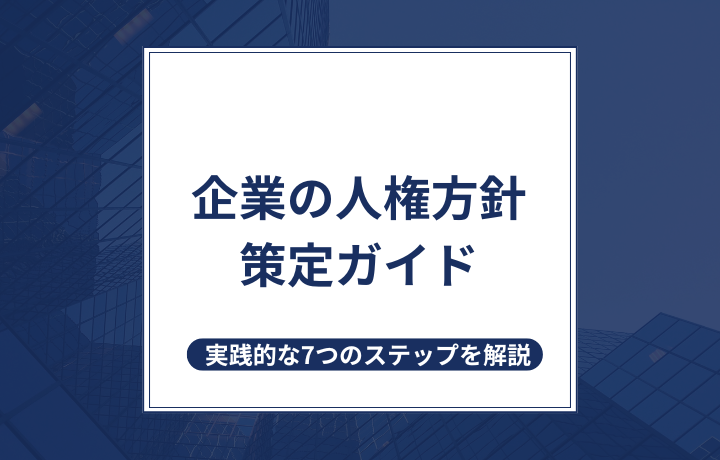
企業が人権尊重の責任を果たすめには、自社の既存方針や慣行がどのような人権課題をカバーしているかを把握し、どの人権課題が未対応なのかを明らかにする必要があります。これが「社内方針のギャップ分析」です。
本記事では、ギャップ分析の目的と意義、実施方法、そしてその結果を人権方針の策定や改定にどう活かすかについて、実践的な視点から解説します。
このギャップ分析は、人権方針を改定する際の手法としても有効です。
なぜギャップ分析が必要なのか?
多くの企業では、長年にわたって蓄積された行動規範や倫理的価値観の中に、実質的に人権を扱っている内容が含まれています。しかし、それらの文書には「人権」という言葉が明示されていないことも少なくありません。
たとえば、以下のような方針が存在していても、それが人権に関わるものであるという認識が社内で共有されていない場合があります。
- 多様性の尊重
- 差別禁止
- ハラスメント防止
- 安全衛生
- 最低年齢規定
- 労働時間の管理
こうした既存方針の中に潜在的に含まれる人権要素を洗い出し、国際的に認められている人権のうち、どれがカバーされていて、どれが欠けているのかを判断することが、ギャップ分析の目的です。
ギャップ分析の実施ステップ
ギャップ分析は、単なる文言の確認ではなく、企業の立場や事業活動に照らして、どの人権が重要であるかを見極める作業です。以下のステップで進めることが推奨されます。
1. 既存方針の収集と分類
企業理念、行動規範、就業規則、安全衛生方針など、社内に存在する関連文書を網羅的に収集します。人権方針の改定する際は、既存の人権方針も合わせてギャップ分析の対象とします。
2. 人権との関連性の評価
各方針がどの人権課題に関係しているかを評価します。国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則12が示すリスト(世界人権宣言、国際人権規約、ILO中核的労働基準)を参照することで、評価の精度が高まります。これらの国際文章は、馴染みのない人が読み解くには難易度が高いため、ステップ3の解説を参照し、外部の専門家に解釈や支援を求めるとよいでしょう。
3. カバーされていない人権の特定
評価の結果、既存の方針や慣行では対応されていない人権課題を特定します。特に、業界特有の課題や事業展開地域の状況に応じて、重点的に対応すべき人権を見極めることが重要です。また、社会的に弱い立場にあるとされる人々の人権への特別な配慮ができているかどうか、実際に影響を受ける人たちから意見をくみ取り、分析に反映することも重要です。
4. 表現の明確化
既存方針に人権に関する文言が含まれていない場合は、明示的な表現に改めることが望まれます。これにより、社内外のステークホルダーに対して企業の姿勢を明確に示すことができます。
ギャップ分析によって得られるメリット
見過ごされていた人権課題を浮き彫りにする
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業は国際的に認められているすべての人権を尊重する責任があるとされています。ギャップ分析を行うことで、企業は人権課題に網羅的に対応できる体制を整えることができます。
社内外の信頼性向上につながる
ギャップ分析を経て策定された人権方針は、単なる理念ではなく、実態に即した内容となります。また、人権方針策定の過程を統合報告書などで示すことによって、社内の従業員や社外のステークホルダーからの信頼を得やすくなります。
実効性のある人権方針の策定につながる
ギャップ分析は、単に「足りないものを埋める」作業ではなく、企業の事業活動に即した人権課題を特定し、優先順位をつけるための基盤となります。これにより、実効性のある人権方針の策定が可能になります。
社内の理解と浸透を促進する
ギャップ分析の過程で、部門横断的な議論や文書の見直しが行われることで、社内の人権に対する理解が深まり、方針の浸透にもつながります。
分析のポイント
1. 状況の変化に対応するための「定期的な評価」
人権課題は時代や社会情勢、事業環境の変化に応じて新たに顕在化することがあります。ギャップ分析は一度きりではなく、定期的に見直す仕組みが必要です。
例えば、グローバル製造業の場合、既存の人権方針では「強制労働」や「児童労働」という文言を明記していることが多いと思います。近年の気候変動に伴う移住労働者の増加に伴い「移住労働者の待遇」や「言語・文化の違いによる差別」が新たな課題として浮上したり、調達先を変更したことで、先住民族の権利の尊重が新たに重要な課題となる場合もあります。定期的なギャップ分析を通じて、これらの課題を新たに方針に反映することが重要です。
2. 業界・地域特有の人権リスクの見極め
世界には多種多様なビジネスが存在しており、それらが人々の人権に及ぼす影響も多種多様です。企業は、自社が展開するビジネス特有の人権リスクを見極めることが重要です。
例えば、IT業界の企業の場合、社内方針に「労働時間管理」や「ハラスメント防止」は含まれていたとしても、「アルゴリズムによる差別」や「プライバシー侵害」への対応が抜け落ちてしまっている可能性も考えられます。